3,113view
フレックスタイム制とは?自由で効率的な働き方に潜むデメリット
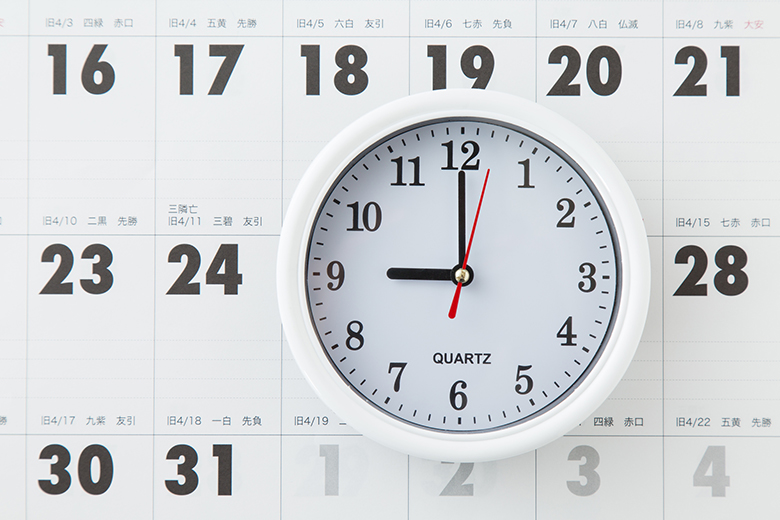
この記事で分かること
- フレックスタイム制とは自分で始業時刻・終業時刻を決めることができる制度
- フレックスタイム制でも、平均して「1日8時間、週40時間」以上働いた場合は残業代が出る
- フレックスタイム制でのトラブルは専門の弁護士に相談しよう!
あともう少し寝ていたい。子供を幼稚園に送ってから出勤したい。早く帰って家事をしたい。こういった願望をかなえる制度として、フレックスタイム制があります。このように聞くと、フレックスタイム制は理想的な働き方だと思えるかもしれませんが、実はデメリットもあります。今回はフレックスタイム制のデメリットについて紹介します。
フレックスタイム制とは?
ひとことでいうと、フレックスタイム制とは自分で始業時刻・終業時刻を決めることができる制度です。
自分で決めるといっても「自分は10時出社にする」と選択して、毎日必ず10時に出社しなければならないというわけではなく、その日その日の都合で自分の選択で変えることができます。
あとで触れるように、フレックスタイム制には自己管理能力が備わっていないと仕事が回らなくなってしまうことや、残業代がごまかされやすいといったデメリットがあります。
コアタイムとフレキシブルタイムって何?
フレックスタイム制について話していると、よくコアタイムとフレキシブルタイムという言葉を聞きます。簡単に説明すれば、コアタイムとは必ず会社にいなければならない時間帯のことをいい、フレキシブルタイムとは自由に自分で管理することができる時間帯のことをいいます。このことについて、詳しくみていきましょう。
コアタイムとは
会社で働いていると、会議が定期的にあったり、ミーティングや打ち合わせをしたりしなければならない時間というのが多くあります。急遽相談しなければならないことも出てくるでしょう。もしそんなときに、自由な働き方をしているからといって社内にいないと、トラブルにつながりかねません。このような問題を解決するのがコアタイムという概念です。
コアタイムとは、上記のように必ず会社にいなければならない時間帯のことです。だいたい10時~15時あたりに設定している会社が多く、もしこのように設定されているとすれば、いくら自由な働き方を認めているからとはいえ10時までには出社し、15時までは会社にいなければなりません。しかし逆にいえば、その他の時間は自由につかえるということを意味しています。
フレキシブルタイムとは
フレキシブルタイムとは、自由に出退勤してよい時間帯のことです。コアタイムが設定されている場合は、コアタイム以外の時間ということになります。この時間は自由に使えるので、「もう少し寝ていたい」「子供を幼稚園に送ってから出社したい」といった労働者の願いをかなえることができます。
変形労働時間制との違い
場合によってはフレックスタイム制も変形労働時間制の一環として用いられることが多く、変形労働時間制の一形態としてみなされることもあります。しかし、変形労働時間制では1日の始業時間と終業時間が会社によって定められているのに対し、フレックスタイム制は自分で1日の始業時間と終業時間を自分で定めることができるという違いがあります。
つまり、変形労働時間制でも出勤時間をずらしたり、特定の日の労働時間を短くしたりすることができますが、それが会社との相談によって決定されるというところに、変形労働時間制とフレックスタイム制の違いがあります。
裁量労働制との違い
フレックスタイム制と裁量労働制は同一のものだろうと考えている方がいますが、しかし、実際には異なっています。裁量労働制とは、デザイナーや弁護士などが多く採用している働き方で、時間の配分が個人の裁量に任せられている場合を意味しています。
これだけを聞くとフレックスタイム制とあまり違いがわからないかもしれませんが、裁量労働制は多く働いても短く働いても給与があらかじめ残業代を含めて設定された額となることが多いのに対し、フレックスタイムは、出退勤は自由だが会社にいたことが実際の労働時間となるため、1週間40時間を超えた場合は残業代が支払われます。
これらは、労働時間自体が個人の裁量に任されているか、労働時間は決められていて、出退勤の時間だけが個人の判断に任せられているかというところに、違いのポイントがあります。
フレックスタイム制の残業代
あとでも触れますが、フレックスタイム制についてしっかりと理解していないと、残業代をごまかされるケースがあります。フレックスタイム制でも残業代は出るのですが、そのことについて「え、うちの会社の説明と全然違うぞ」と思う方もいるかもしれません。
これはフレックスタイム制が、実際には経営者側の都合のいいように解釈されて導入されているケースになります。
2019年4月以降におけるフレックスタイム制の改正
フレックスタイム制を理解する上で知っておかなければならないのは、2019年4月以降とそれ以前では、法律の改正によって少し内容が異なるという点です。改正のポイントは清算期間の延長が可能になった点と、週あたりの労働時間の変更です。
清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月へ
フレックスタイム制では、一定の期間で労働時間を総合して残業代を計算します。
簡単にいえば、その残業代を計算する期間を清算期間といいますが、それまでのフレックスタイム制では、この清算期間が1ヶ月でした。つまり1ヶ月内の労働時間が1週間あたり40時間を超えていれば、残業代が出ました。
しかし、改正後はこの清算期間が3ヶ月以内になります。つまり、4月は忙しかったために週あたり50時間働いていたが、5月と6月は暇で週あたり35時間しか働かなかったという場合は、この2ヶ月を合わせて精算して、残業はなかったとすることが可能になったのです。
1ヶ月を超える清算期間を設ける場合は、労使協定に明記し、労働基準監督署に提出していなければならないため、もし記載がないのに清算期間が延長されている場合は、専門の弁護士に相談することも検討しましょう。
週あたりの労働時間の上限が50時間へ
法定労働時間は、通常「1日8時間、週40時間」です。フレックスタイム制で、3ヶ月の清算期間を採用している企業でも、3ヶ月の平均はこの通り「1日8時間、週40時間」で、それ以上働いた場合は残業代を支払わなければなりません。しかし改正後は、平均がこの通りであれば、週50時間以内の労働でも残業代を支払わなくてもよくなりました。
4月が週あたり50時間、5月が30時間となれば、残業代はないということです。しかし一方で、それまでは特例業種のみ週あたり44時間でもよいとされていましたが、清算期間が1ヶ月を超える場合は、この特例業種であっても平均して「1日8時間、週40時間」以上であれば残業代を支払わなければならないとなりました。
もし3ヶ月の清算期間なのに、2ヶ月しか働かなかった場合は?
もし清算期間が3ヶ月だと定められているのに、2ヶ月しか働かなかった場合はどうなるのでしょうか。この場合は、2ヶ月間の平均労働時間が週40時間以上であれば、残業代は支払われると定められています。
つまり、4月と5月は週あたり50時間で労働し、6月は仕事がなく出勤しなかったという場合に、「3ヶ月の労働時間を平均すると週40時間の範囲内だから残業代は支払わない」ということはあり得ないということです。もしこのようなことがあったら、弁護士に相談するようにしましょう。
フレックスタイム制のデメリット
社員の労働力を搾取したいと考える経営者は、フレックスタイム制を「いくら働かせても、残業代を支払わなくてもよい制度」 と考えている場合が少なくありません。次に、フレックスタイム制のデメリットを紹介します。
導入自体が適法でない可能性もある
フレックスタイム制を導入している会社の中には、そもそも導入の方法自体が適法ではない可能性がある会社もあります。
特に就業規則や労使協定にフレックスタイム制の導入の旨が書かれていないことや、1ヶ月を超える清算期間を設けているのにそれが明記されていない場合、また契約上はフレックスタイム制のはずなのに毎日の出退勤時間を強制されている場合などは、すぐに弁護士に相談した方がよいかもしれません。
残業代をごまかされやすい
フレックスタイム制を導入している場合、1日の労働時間があいまいになりやすいという特徴があります。そのため、自分で毎日記録していないと、あとで計算してみたら実際には平均労働時間が1日8時間、週40時間以上だったということにもなりかねません。
この場合でも残業代が支払われていればまだ救われるのですが、そうでない場合もあるので、自分でしっかり管理しておく必要があります。清算期間内の平均労働時間が1日8時間、週40時間以上だった場合は、残業代を請求するようにしましょう。
フレックスタイム制のトラブルは弁護士に相談!
フレックスタイム制とは、自分でその日その日の始業時刻・終業時刻を決めることができる制度です。正しく導入されている場合は理想的な制度になり得ますが、残業代をごまかされやすいというデメリットがあります。
また2019年4月以降は制度が若干変わっていますので、注意が必要です。もしフレックスタイム制でトラブルが起きている場合は、専門の弁護士に相談することを検討しましょう。
- サービス残業、休日出勤がよくある
- タイムカードの記録と実際の残業時間が異なる
- 管理職だから残業代は支給されないと言われた
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
- 自主退職しなければ解雇と言われた
- 突然の雇い止めを宣告された
